「上司にどうやって声をかけたらいいんだろう…」
「どのように退職理由を伝えたらいいんだろう…」
退職を決意したものの、話しの切り出し方がわからず、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
伝え方を間違えてしまうと退職を引き止められたり、職場の人間関係を悪化させる可能性もあるので、まずは正しい方法を知る必要があります。
この記事では円満退職を実現させるために重要となる、上司とのアポイントメントの取り方、失敗しない退職の伝え方について解説します。
退職を切り出す最適な時期
上司とのアポイントメントを取る前に、退職を伝える適切なタイミングをおさえておきましょう。
円満に退職するためには、以下の内容を考慮する必要があります。
退職を伝えるのは3ヶ月以上前が理想
退職の意思を伝えるタイミングは、退職希望日の3ヶ月以上前が理想です。
会社としては、退職希望者が出ると後任者を探し、その後任者の業務も調整しなければならず、かなりの時間がかかります。
そのため、多くの会社では『退職日の○ヶ月前までに申し出る』という就業規則を定めています。
円満退職を目指すなら、引き継ぎや有給休暇の期間も考慮し、就業規則よりも早めに意思を伝えましょう。可能であれば、3ヶ月以上前には伝えるのが望ましいです。
また、民法上では退職希望日の2週間前までに申し出れば退職できると定められていますが、会社側の都合を考えると、2週間で引き継ぎを完了させるのは現実的ではありません。
退職の意思をギリギリに伝えると、引き継ぎの時間が不足し、トラブルにつながることが多いです。円満退職を目指すなら、できるだけ早めに行動するようにしましょう。
「退職伝えるの早すぎるかな?」と心配な場合
「退職を3か月以上前に伝えたら、引き止められるのでは……」
「会社に居づらくならなったらどうしよう‥‥‥」
このように不安を感じて、なかなか行動に移せない方もいるかもしれません。
しかし「退職を伝えるのが早すぎて失敗した」というケースは少なく、むしろ後回しにする方がリスクが高くなります。そのため、できるだけ前倒しで伝えるのが理想的です。
早めに伝えることで、十分な引き継ぎ期間を確保でき、有給休暇の消化もしやすくなります。
また、決算のように1年に一度や半年に一度しかない業務は、引き継ぎのタイミングを逃すと実際に経験しながらの引き継ぎができないため、早めに伝えることでスムーズに退職準備を進められます。
「伝える時期が早いか遅いか」ではなく、「転職先の内定が決まった」「退職後の具体的なプランが固まった」タイミングを目安にし、会社へ退職の意思を伝えることが重要です。
繁忙期は避けるよう配慮する
忙しい時期に退職の意思を伝えると、業務負担が増え、上司や同僚に迷惑をかけるおそれがあります。
ただでさえ忙しいため、退職者への対応に手が回らないことも少なくありません。
「こんな忙しい時期に、まったく配慮がない…」
「なんでいま、退職の話をしてくるの…」
このように思われ、職場の人間関係が悪くなるケースがあるので注意が必要です。
また、繁忙期は引き継ぎのための時間を確保しにくく、十分な準備ができない可能性があります。その結果、退職を引き止められることもあるため気を付けましょう。
決算期や大規模なプロジェクトの進行中なども避け、できるだけ業務が落ち着くタイミングを選ぶことで、円満に退職しやすくなります。
上司とのアポの取り方|3つのポイント
退職を円滑に進めるためには、上司を呼び出す方法にも気を配る必要があります。
トラブルなく上司を呼び出すための重要点を3つお伝えします。
①伝えるのは直属の上司
退職の意思を最初に伝える相手は、直属の上司です。
職場によっては上司が複数いることもありますが、その時は普段「有給休暇」を申請している相手が直属の上司にあたります。
「退職の話は総務や人事にするものでは?」
このような思い込みから、人事担当者に直接伝えてしまうと、余計なトラブルを招く可能性があります。直属の上司を飛ばしてしまうと、「無視された」と捉えられ、信頼関係が崩れる要因にもなりかねません。退職日までは一緒に働くことになるため、職場の雰囲気が悪くなり、仕事がしづらくなる恐れがあります。
退職の意思を上司に伝えた後は、その上司の指示に従いながら社内の退職手続きを進めます。
そのため、周囲にむやみに退職の話をするのは控えたほうが無難です。
「直属の上司がどうしても話を聞いてくれない…」
このような場合は、他の上司に適切な方法で伝えるようにしましょう。
②退職を匂わせない
上司に声をかける際は、退職の話だと悟られないよう注意しましょう。
話し合いの前に退職の意思が伝わってしまうと、交渉が不利に進む可能性があります。
【退職交渉が不利に進んだ事例】
・話し合いを避けられ、時間稼ぎをされる。
・「退職を思いとどまらせよう」と、事前に対策を練られる。
・アポイントメントの段階で「退職するの?」と聞かれ、不意の対応を強いられる。
そのため、上司にアポイントを取る際は、「退職」を意識させないよう配慮が必要です。
【OKな声かけ】
- 「今、少しお時間ありますか?」
- 「お話ししたいことがあるので、少しお時間いただけますか?」
- 「明日の○○時にお時間をいただきたいのですが。」
【NGな声かけ】
- 「退職についてお話ししたいのですが…」
- 「今後についてお話があります。」
- 「相談したいことがあるので、お時間いただけますか?」
上司に「おっ!なんだろう?」と気にさせつつ、退職とは結びつかない言い回しを意識しましょう。
退職を連想させる表現は避け、慎重にアポイントを取りましょう。
③上司に声をかけるタイミング
退職に関する話題は、職場内で無用な混乱や不安を引き起こす可能性があります。また、人間関係に悪影響を及ぼすこともあるため、オープンにしないのが鉄則です。
そのため、上司に声をかけるタイミングは、周囲に人がいない時間帯を狙いましょう。基本的には、昼休みや就業後など、業務時間外が理想です。
事前にメールや電話でアポイントを取る場合も、退職の話を切り出すのは業務時間外が確実です。
ただ、上司から勤務時間内での面談を指定された場合は、その指示に従いましょう。
退職する意思の伝え方|3つのポイント
上司との面談が決まったら、あとは退職の意思を伝えるだけです。
ここでは、退職の意思を切り出す際に意識すべき3つのポイントを解説します。
①会社への不満は言わない
退職理由を聞かれた際に、「会社への不満」や「待遇の悪さ」などネガティブな面を強調するのは避けましょう。
ネガティブな退職理由を伝えた場合、「改善するから残ってほしい」と引き止められる可能性がありますし、考え方をあらためるよう諭されるリスクもあります。
不満を伝えたところで円満退職につながるわけではありません。退職が認められてたとしても、上司との関係が悪くなり、退職日まで気まずい状態で仕事を続けることになりかねません。
円満退職を目指すなら、ネガティブな理由ではなく前向きな退職理由を準備しましょう。
③相談ではなく「退職する意思」を伝える
上司に退職の意思を伝える際に重要なのは「退職を考えている」ではなく、「退職を決意している」ことを明確に示すことです。
「今退職を考えているんです…」といった曖昧な伝え方をすると、上司は「まだ迷っているんだな」と捉え、強く引き止めてくる可能性があります。
退職の意思が固いことを、はっきりと伝えましょう。
【OK】
突然のことで申し訳ありません。
一身上の都合により退職を決意したため、本日お時間をいただきました。
【NG】
今、退職を検討していまして‥。その相談で本日お時間をいただきました。
「相談」ではなく、「意思決定の報告」と考え、上司に納得しやすい退職理由を準備したうえで伝えることが大切です。
また、具体的な退職日は、会社との話し合って決めた方がトラブルを避けやすくなります。
退職を切り出す際には、おおよその退職時期を伝えるようにしましょう。
③退職理由は会社が介入できないものにする
上司に退職の意思を伝えた後、退職理由を詳しく問われる可能性があります。
そのため、会社が介入できない明確な理由を準備し、上司を納得させることが大切です。
以下のような、会社側が引き止めにくい退職理由を伝えるのがポイントです。
【会社が介入できない退職理由】
〇個人の生き方
「今しかできない○○にチャレンジするため、退職を決意しました。」
〇関心があった別業界への転職
「以前から興味があった○○業界への転職を決めました。」
〇家族に関する理由
「親の体調が悪くなり、実家の店を継ぐことになりました。」
個人の生き方や家庭の事情は、会社が干渉しにくい領域です。
自分の意思をしっかりと伝えることで、退職理由に説得力を持たせ、引き止められにくくなります。
まとめ
本記事では、退職を切り出すタイミング、上司とのアポイントの取り方、そして退職の伝え方について解説しました。
【本記事で解説した、円満退職のために意識すべきポイント】
- 退職の意思は3ヶ月以上前に伝える
- 繁忙期を避けて退職の意思を伝える
- 直属の上司に最初に伝える
- 退職を匂わせずにアポイントを取る
- 退職の「相談」ではなく「決意の報告」として伝える
- 退職理由は会社が介入できないものにする(個人の生き方・家庭の事情)
- 会社への不満は言わず、前向きな理由を準備する
退職日までは、これまで通り業務に取り組むことが大切です。
退職の伝え方を誤ると職場の人間関係がギクシャクする可能性があるため、慎重に進めましょう。
早めの準備と適切な伝え方を心がければ、円満に退職を進めることができます。
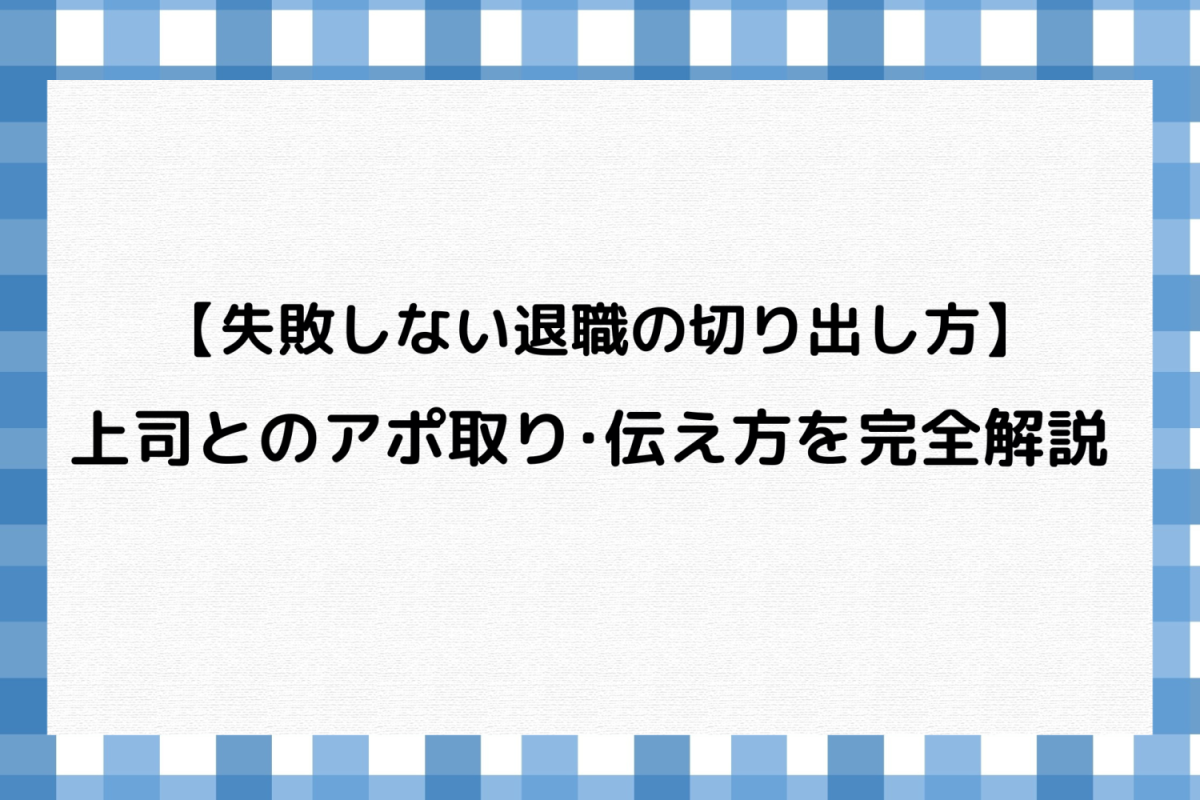
コメント